大きくたくましい身体や、筋肉質な肉体を手に入れたい人もいるのではないでしょうか。
身体を大きくしたい人は増量期と減量期を使い分けることが大切です。一度身体を大きくしてから絞ることで、元の体型よりも筋肉をきれいに見せることもできます。
増量期と減量期が大切な理由や、やり方、トレーニング法を紹介しますので、参考にしてください。
関連記事:減量のやり方とは?筋肉を残しながら脂肪を落とす食事法やトレーニングメニュー
【PICK UP】

トレーニングやダイエットするならプロテインがおすすめ!
プロテインには筋肉を作るために必要なタンパク質が豊富に含まれています。
他にもタンパク質には髪の毛や、爪、肌を作る成分にもなっているため、美容面にも効果的。
ぜひこの機会にプロテイン生活を始めてみてください!!
Myprotein
国内最安値級の低価格と、60種類以上の豊富な味・フレーバーが特徴的。
ボディメイクからダイエット中の栄養補給まで、様々なシーンでお手軽に利用できるプロテインです。
LÝFT
国際ボディビルディング・フィットネス連盟(IFBB)プロ選手、エドワード加藤がプロデュースしているプロテイン。業界最高水準のタンパク質含有量を実現し、味のバランスとコストパフォーマンスにこだわったホエイプロテインです。
増量期と減量期とは?

増量期と減量期とはどのよう時期なのか気になる人もいるのではないでしょうか。
各時期について解説します。
増量期とは
増量期とは体重を増やし、身体を大きくする時期です。
増量期の時期に食事を多くとりエネルギーをためて、高負荷のトレーニングで筋肥大させていきます。
食べる量も体重が増えるように計算して、必要以上のカロリーを摂取することが重要です。カロリーを多くとることで脂肪も一緒に蓄えられてしまいますが、うまくコントロールすれば、脂肪量もあまり増やさずに増量できます。
トレーニングにおいてもどんどんと重量を上げていき、筋肉を刺激していくことが重要です。増量期間中は扱える重さにこだわってトレーニングしていきましょう。
減量期とは
減量期とは筋肉を残しつつ、脂肪を落として体重落とす時期です。
特にこの減量期に食事や、トレーニングの管理ができていないと、増量期に増えた筋肉量も減っていってしまいます。
減量期は体重が減っていくためトレーニングで扱える重さも減少傾向になりますが、なるべく落とさないように維持することが重要です。
食事に関してもカロリーコントロールが重要となり、一気に体重を落とすと思っていたよりも細くなってしまうので注意してください。
ボディメイクに増量期と減量期が必要な理由

マッチョで身体の大きい人は、トレーニングだけで大きくなったと思われがちです。
実際には増量期を作ることで体重を増やし、身体を大きくしています。細い状態のまま筋トレだけを続けていても一定のところまでは大きくなりますが、ボディビルダーのような太さにはなりません。
ボディビルダーのようなたくましい体をつくるためには、増量期に身体を大きくし、脂肪だけを削る努力が大切です。この脂肪だけを削る時期を減量期とも言います。
よくトレーニングすると太くなると思われがちですが、食事とトレーニングを管理すれば太くはならないので安心してください。
増量期を取り入れるメリット

増量期は身体を大きくする以外にもさまざまなメリットがあります。
どのようなメリットがあるのかを解説しますので、参考にしてください。
筋肥大させるため
増量期の最大の目的は筋肥大させるためです。
理想の体型を手に入れるためには体重を増やして、脂肪を付けたくないのが本音だと思います。筋肥大させるためには1日の必要カロリーよりも、摂取カロリーを大きくしなければなりません。
減量時の食事を続けていると栄養が不足してしまうこともあり、筋肉が肥大しない原因にもなります。効率よく筋肉を肥大させるためにも、増量期は重要です。
トレーニング後は栄養を吸収しやすい状態となっています。食事を多くとることで筋肉を効率よく肥大させることも可能です。
筋肥大については「筋肉の付け方とは?効果的なトレーニング法も解説」も参考にしてください。
免疫力を向上させるため
トレーニングで体脂肪率を落とした状態を続けると、免疫力が低下する原因にもなります。
これは脂肪量が少ないため、体温が下がってしまうことが原因です。
特に冬場など体温を下げやすい時期に体脂肪が少ない状態だと、体調を崩しやすくなってしまいます。
オフシーズンでもある冬場は増量期にして、免疫力を高めておくことも重要です。
特に冬に体調を崩しやすい人は、体脂肪率の管理もしっかりとするようにしましょう。
増量期が必要な人

増量期を取り入れるのおすすめの人は、下記のような目的がある人です。
- 体を大きくしたい人
- コンテストに出場したい人
それぞれについて解説していきます。
体を大きくしたい人
身体がガリガリで筋肉をつけたい人や、今よりも太い筋肉を手に入れたい人は、増量期を作りましょう。
筋トレを始めたばかりの頃は筋肉もついていきますが、ある程度のところまで行くと止まってしまいます。筋肉は体重が増えるにつれて、一緒に増えていくものです。体脂肪もついてはしまいますが、増量期は割り切ることも重要です。
太らないようにカロリーコントロールをしている状態だと、なかなか筋肉も大きくなっていきません。
筋肉をつけていくためにも、オーバーカロリー(消費カロリーよりも摂取カロリーが多い状態)を作り、体重を増やしていくようにしましょう。
コンテストに出場したい人
ボディビルやフィジーク、ベストボディなどの筋肉の美しさを見せるコンテストに出場したい人は、増量期を取り入れるようにしましょう。
出場するコンテストによっては、筋肉の大きさも重要になることがあります。きれいな筋肉美が作れていても、細いと良い順位を狙えないことも。
コンテストに出場したい人は、参加者がどのくらいの大きさがあるのかもチェックしておくことが重要です。
大きさが足りない場合には、コンテストのないオフシーズンを利用して、増量期を取り入れるようにしましょう。
増量の方法

増量はバルクアップとも言い、方法は主に3種類あります。
- リーンバルク
- クリーンバルク
- ダーティーバルク
それでは各バルクアップの違いについて解説していきます。
リーンバルク
リーンバルクとは体脂肪をあまり付けないように、カロリーをコントロールしながら行うバルクアップ法です。
消費カロリーと摂取カロリーのバランスを考えたうえで、食べる量を計算する必要があります。増量するときには体重の増え方や、体脂肪率の増え方に注意しながら行うことが重要です。
リーンバルクは脂肪がつきにくいため減量が楽になるのがメリットですが、ゆっくりと体重が増えていくため、一気に増量したい人にとってはデメリットとなってしまうこともあります。
ゆっくりと増量をしていきたい人や、健康的に体を大きくしていきたい人は、リーンバルクを取り入れるようにしましょう。
リーンバルクは「リーンバルクとは?やり方やPFCバランス・カロリーの計算方法も解説」も参考にしてください。
クリーンバルク
クリーンバルクとは身体に良いものを食べながら、大きく増量していく方法です。食べる量に制限はありませんが、ジャンクフードなどは食べません。
PFCバランスを考えながら、必要な栄養素の含まれている食品を、カロリー制限なく食べていきます。
食べるものにこだわりをもつため、身体への負担が少なく増量ができるのがメリットです。また、食べるものの制限もあまりないため、ストレスなく進められるのも魅力と言えます。
体脂肪をあまり付けずにキレイな増量をしたい人は、クリーンバルクを取り入れるようにしてみてください。
クリーンバルクは「クリーンバルクとは?正しいやり方やPFCバランスも解説」も参考にしてください。
ダーティーバルク
ダーティーバルクとはその名のとおり、食べるものや、摂取カロリーに関係なく、好きなものを食べて行う増量法です。
クリーンバルクでは食べるものにこだわりましたが、ダーティーバルクではジャンクフードや、お菓子、油モノなど、気にせずに何でも食べていきます。
とにかく消費カロリーよりも摂取カロリーを多くして、体を大きくしていくことが重要です。
食べるものに制限がないので、ストレスなく続けられるのが最大の魅力と言えます。
ただし必要な栄養素が取れていなかったり、体脂肪がつきやすくなったりしてしまうため、減量を考えている人にはおすすめできない増量法です。
ダーティーバルクは「ダーティーバルクとは?メリット・デメリットや摂取すべきカロリーも紹介」も参考にしてください。
増量期と減量期のタイミングや期間

増量期と減量期は計画的に作るようにしましょう。
増量期では自分の目標となる体重まで3~6か月かけてゆっくりと増やしていきましょう。急激に増やしすぎると身体への負担が大きくなり危険です。
ペースとしては1か月当たり2~3kgほどとなります。
減量期に入るタイミングは、増量期で満足いく太さになってからです。基本的には増量期の時が一番太い状態で、そこから絞っていくので細くなっていきます。
減量期も急激に痩せると必要以上に筋肉が落ちてしまい、思っていたよりも細くなってしまうので注意が必要です。
減量するときには1か月あたり体重の3~5%を目安に落としていきましょう。
筋肉をきれいに見せるためには、体脂肪率を1ケタ台まで落とす必要があります。
カロリーについては「ダイエット時に重要なカロリー制限について」も参考にしてください。
増量期と減量期におすすめの食事法

増量期と減量期の食事はどのようにしたら良いのか、気になる人もいるのではないでしょうか。
ここではおすすめの食事法を紹介しますので、参考にしてみてください。
栄養バランスは「筋トレに理想のPFCバランスは?摂取量の計算方法も解説」も参考にしてください。
増量期の食事
増量期には消費カロリーよりも多く摂取する必要があります。
まずは1日に最低限必要なタンパク質量を摂取しましょう。増量期に必要な摂取量の目安は、体重1kgあたり2gです。
タンパク質量で足りないカロリーを炭水化物と脂質で補っていきます。
炭水化物は身体を動かすためのエネルギーになるため、高重量扱う増量期では必要以上に摂取することが重要です。また、炭水化物にはタンパク質の吸収を良くする働きもあります。
脂質については足りない分を補う形で摂取しましょう。脂質はタンパク質や炭水化物よりも1gあたりのカロリーが高いのが特徴です。
なるべくカロリーを増やすときにはタンパク質と炭水化物で補うようにすることで、余計な脂肪もつかずに増量ができます。
減量期の食事
減量期の食事は増量期と同じように、まずはタンパク質量の必要量を摂取しましょう。
タンパク質量の摂取の目安は体重1kgあたり2gです。
このタンパク質量を摂取したときに何kcalになるかを計算します。
タンパク質のカロリーが計算できたら、炭水化物の摂取量を計算しましょう。
減量中は摂取カロリーが少なるため、空腹感が強くなります。空腹感がつらい時は野菜や、果物を食べるようにしましょう。
特に葉野菜はカロリーが少なく食物繊維が豊富なため、空腹感を満たすのにおすすめです。
空腹については「ダイエット中は寝る前に空腹にすべき?食べても良い食品も紹介」も参考にしてください。
増量期と減量期におすすめのトレーニング法

増量期と減量期ではトレーニングの目的が少し異なります。
おすすめのトレーニング法を紹介しますので、参考にしてください。
トレーニングメニューについては「【筋トレ初心者必見】トレーニングメニューの組み方とは?」も参考にしてください。
回数とセットの設定方法
回数はトレーニングの目的によって、変更することが重要です。
回数とセット数は、下記のように設定しましょう。
| 目的 | 回数 | セット数 |
| 筋肥大 | 8~12回 | 3~5セット |
| ダイエット | 20回 | 3~5セット |
筋肥大をターゲットとしている場合には10回を目安にするのがおすすめです。
セット数は3~5セットで組みましょう。6セット目以降もできそうな場合には、負荷を上げるのがおすすめです。
トレーニングの回数やセット数は「筋トレの負荷・回数・セット数はどうやって決める?目的別の正しい設定方法を解説」も参考にしてください。
トレーニング負荷
トレーニング負荷も目的によって設定方法が異なります。
トレーニング負荷の設定方法は、下記のとおりです。
| 目的 | 負荷 |
| 筋肥大 | 8~12RM |
| ダイエット | 20RM |
RMとは「レペティション・マキシマム」の略で、最大反復回数のことです。例えば10RMの場合には、10回で限界に達して、11回目ができない重量となります。
自宅でするときにはダンベルや、ペットボトル、チューブなどで代用しましょう。
自重トレーニングなどの重量で負荷を変更できないときは、メニューを変更するのもおすすめです。特にジャンプ系の種目は運動強度が高いため、自重トレーニングに慣れてきたら取り入れてみてください。
セット間のインターバル
トレーニングはセットごとにインターバルをとりましょう。しっかりと休むことで、次のセットも最後まで追い込めるようになります。
インターバルの目安は、下記のとおりです。
| 目的 | インターバル |
| 筋肥大 | 1分~1分30秒 |
| ダイエット | 30秒 |
ダイエットが目的の場合は、インターバルを短くして追い込むようにしましょう。
インターバル中は水分補給や、トレーニングフォームを見直し、呼吸を整えることに集中しましょう。
インターバルは「筋トレのインターバルはどのくらいとる?おすすめの時間を解説」も参考にしてください。
トレーニング頻度
トレーニングの方法としては2パターンあり、1日に全身やる方法と部位別に行う方法です。
全身トレーニングするときは週に2~3日ほどしましょう。
連日トレーニングするのではなく、トレーニング後48~72時間あけるようにしてください。
週に4日以上トレーニングする場合には、身体を部位別に分けて行います。
例えば胸、背中、脚、腕と4部位に分けましょう。このように分けることで、部位を回復させながら効率よく鍛えられます。
筋トレ初心者の時は週2~3日、全身を鍛えるのがおすすめです。
トレーニングに慣れてきたら部位別に分けて、効率を上げていきましょう。
トレーニング頻度は「筋トレには休息日が大切!効果的なトレーニング頻度も解説」も参考にしてください。
トレーニング種目例

上半身と下半身をバランスよく鍛えることのできるトレーニングメニューを紹介していきます。初心者編と上級者編の2つ紹介しますので、どのようなトレーニングをしたら良いのか悩んでいる人は、参考にしてみてください。
トレーニングメニューについては「1週間の筋トレメニューを紹介!これで迷わずトレーニング」も参考にしてください。
初心者編
ここではトレーニングを始めたばかりの人や、これから始めようとしている人におすすめのトレーニングを紹介します。簡単なウエイトマシンを中心に紹介していますので、参考にしてください。
レッグプレス
レッグプレスは下半身を中心に鍛えるウエイトマシーンです。主に大腿四頭筋や、ハムストリングス、大殿筋を鍛えられます。
レッグプレスの使い方は、下記のとおりです。
- 脚をフットプレートの位置に置く
- 膝が90度になるようにイスの位置を調整する
- イスを調整できたら、脚でフットプレートを押し、足を伸ばす
- 元の位置に戻る
足を伸ばすときは、膝を伸びきらないようにするのがポイントです。足が内股にならないように、つま先・膝・肩が一直線になるようにしましょう。
レッグプレスについては「レッグプレスの正しいやり方と効果を最大化させる方法を解説」も参考にしてください。
チェストプレス
チェストプレスは胸を鍛えるウエイトマシーンです。主に大胸筋が鍛えられます。
チェストプレスの使い方は、下記のとおりです。
- バーの位置が胸の一番高いところに来るように、イスの高さを調整する
- グリップを握った時に、肩がきつくない位置に、バーを設定する
- 背もたれに背中と頭をしっかりと付ける
- バーを前に押し出す
- ゆっくりと元の位置に戻す
バーを押した時に、背中が背もたれから離れないように注意しましょう。肘が伸びきらない、ギリギリの位置にするのがおすすめです。
チェストプレスについては「チェストプレスのやり方や効果を最大化させる方法を解説」も参考にしてください。
ラットプルダウン
ラットプルダウンは背中を鍛えるウエイトマシーンです。広背筋を鍛えることで、逆三角形の身体をつくれます。
ラットプルダウンの使い方は、下記のとおりです。
- フットバーの下に脚をいれ、固定できる位置に調整する
- 一度立ち上がり、バーを肩幅から拳2つ分くらいの位置で握る
- バーを握ったまま、イスに座る
- 鎖骨に向かってバーを下ろす
- 肘を伸ばしながらバーを戻す
バーを下ろすときに、背中が丸まらないように注意しましょう。バーを戻すときには重さに頼らずに、ゆっくりとコントロールしながら戻してください。
ラットプルダウンについては「ラットプルダウンのやり方や効果を最大化させる方法を解説」も参考にしてください。
ショルダープレス
ショルダープレスは肩を鍛えられるトレーニングマシーンです。三角筋を鍛えることができ、たくましい肩幅を作れます。
ショルダープレスの使い方は、下記のとおりです。
- イスに座った時にバーが耳たぶの高さに来るように、イスの高さを調整する
- バーをしたから握る
- バーを天井に向かって持ち上げる
- ゆっくりと元の位置まで下ろす
背もたれに背中を付けた状態でやるのがポイントです。
バーの握る位置によって、肩の前側を鍛えることもできます。
ショルダープレスについては「ショルダープレスのやり方や効果を最大化させる方法を解説」も参考にしてください。
アームカール
アームカールは前腕を鍛えるトレーニングです。前腕を鍛えることで、力こぶを作れます。
アームカールのウエイトマシーンがおいてあるジムは少ないので、ダンベルで代用するのがおすすめです。
アームカールは、下記のようにやります。
- 手のひらを上にしてダンベルを握る
- 肘をわき腹に固定する
- ダンベルを持ち上げる
- ダンベルを下す
ダンベルを持ち上げたり、下ろしたりするときは、肘の位置を動かさないようにしましょう。疲れてくると下ろす距離が短くなってしまうので、肘が伸びきるところまで下ろすのを意識してください。
アームカールについては「アームカールのやり方と効果を最大化させる方法を解説」も参考にしてください。
フレンチプレス
フレンチプレスは二の腕(上腕三頭筋)を鍛えるトレーニングです。二の腕の引き締めや、たるみの解消に効果があります。
フレンチプレスのやり方は、下記のとおりです。
- ダンベルを両手で持ち、頭の上に持ち上げる
- 背中側に肘を曲げる
- 肘を曲げたら、頭の上に持ち上げる
肘が90度になる位置まで曲げましょう。トレーニングは可動域が大きくなるほど、効果が高くなります。ダンベルを持ち上げるときは、天井に向かって押すように持ち上げるのがポイントです。
フレンチプレスする時はダンベルだけでなく、プレートなども利用して鍛えられます。
フレンチプレスについては「フレンチプレスのやり方と効果を最大化させる方法を解説」も参考にしてください。
クランチ
クランチは腹筋を鍛えるトレーニングです。シックスパックに割れた腹筋や、くびれのあるお腹を作るのにおすすめ。
クランチのやり方は、下記のとおりです。
- 床に軽く膝を曲げて、仰向けで寝る
- 手を太ももの上におき、擦りながら上がる
- 元の位置にゆっくりと戻る
上体は最後まで起き上がらせる必要はありません。40度ほど起き上がっていれば、腹筋に効果があります。
腹筋するときに、手を頭の後ろで組むのをやめましょう。疲れてきたときに手で上げてしまい、いきおいで首をケガしてしまうこともあります。手の位置は太ももの上に置くのがおすすめです。
クランチについては「【お腹痩せ筋トレ】クランチの正しいやり方と効果を高める方法」も参考にしてください。
レッグレイズ
レッグレイズは腹筋の下部を鍛えるトレーニングです。ポッコリお腹の改善や、下腹が出てくるのを防ぐ効果があります。
レッグレイズのやり方は、下記のとおりです。
- 脚を天井に上げて、仰向けで寝る
- 脚を床に向かって下ろす
- 脚を床ギリギリまで下げたら、ゆっくりと持ち上げる
脚を下した時に腰が痛い人は、手をお尻の下に入れることで軽減できます。
足を伸ばした状態でやるのがきつい人は、膝を90度に曲げた状態から、曲げ伸ばしをするのもおすすめです。
レッグレイズについては「【下腹部の筋トレ】レッグレイズの正しいやり方と効果的な方法」も参考にしてください。
上級者編
ここではトレーニングに慣れてきた人や、もっと効率よく鍛えたい人におすすめのトレーニング種目を紹介します。筋トレ上級者の人はウエイトマシンだけでなく、BIG3などのフリーウエイトトレーニングを取り入れるのがおすすめです。
筋トレ上級者におすすめのトレーニング種目を紹介しますので、参考にしてください。
スクワット
スクワットは下半身を中心に鍛えるトレーニングです。主に大腿四頭筋や、ハムストリングス、大殿筋を鍛えていきます。
スクワットのやり方は、下記の通りです。
- 脚を肩幅に開く
- お尻を後ろに引きながら、太ももが床と平行になるまでしゃがむ
- ゆっくりと立ち上がる
しゃがんでいくときは、膝がつま先よりも前に出ないように、お尻を後ろに引きながらするのがポイントです。
また、内股になってしまわないように、しっかりと足を開いてするようにしましょう。
スクワットについては「ヒップアップにはスクワット!美尻に効果的なやり方も紹介」も参考にしてください。
ランジ
ランジもスクワット同様に、下半身を鍛えるトレーニングです。主に大腿四頭筋や、ハムストリングスを中心に鍛えられます。
ランジのやり方は、下記のとおりです。
- 脚を前後に開く
- 前脚が90度になるまで膝を曲げながらしゃがむ
- 元の姿勢に戻る
反対側の脚も同様に鍛えていきます。
前膝が内側に入らないように、つま先に向かって真っすぐと曲げるようにしましょう。内側に入っていってしまうと、ひざを痛める原因となってしまいます。
ランジについては「【脚痩せ筋トレ】ランジのやり方や効果的に鍛える方法を紹介」も参考にしてください。
ベンチプレス
ベンチプレスは胸周りや、二の腕を鍛えるトレーニングです。主にバストアップや、分厚い胸板、引き締まった二の腕を作る効果があります。
ベンチプレスのやり方は、下記のとおりです。
- バーベルの真下に目線が来るように、ベンチに仰向けで寝る
- 床に両足をつけ、マットに頭・背中、お尻をくっつける
- バーベルを下ろした時に肘が90度になる位置でバーを握る
- ラックアウトして、胸の一番高い位置に動かす
- 肘を曲げながら、バーベルが胸につくまで下ろす
- バーベルを元の位置まで持ち上げる
バーベルを持ち上げるときに手首が曲らないように注意しましょう。手首が曲ってしまうと、うまく力が伝わりません。
バーベルを下ろすときには左右のバランスに気を付けてください。慣れるまでは左右差が出てしまい、先に利き腕だけ疲れてしまうこともあります。
ベンチプレスについては「【胸の筋トレ】ベンチプレスのやり方と効果を高める方法」も参考にしてください。
デッドリフト
デッドリフトは腰回りの筋肉を鍛えるトレーニングです。デッドリフトをすることで腰痛の予防や、姿勢改善にも効果があります。
デッドリフトのやり方は下記のとおりです。
- 足を肩幅に開いて立ち、バーベルを順手で握る
- スネと太ももに沿わせながら、バーベルを持ち上げる
- 持ち上げきったら、床にゆっくりと下ろす
腕の力を使ってバーベルを持ち上げるのではなく、腰と足を使って上げるのがポイントです。バーベルを下ろすときは膝を曲げながら、ゆっくりと下ろすようにしましょう。
デッドリフトについては「【背中の筋トレ】デッドリフトの正しいやり方と効果を高める方法」も参考にしてください。
ショルダープレス
ショルダープレスは肩を鍛えられるトレーニングマシーンです。三角筋を鍛えることができ、たくましい肩幅を作れます。
ショルダープレスの使い方は、下記のとおりです。
- イスに座った時にバーが耳たぶの高さに来るように、イスの高さを調整する
- バーをしたから握る
- バーを天井に向かって持ち上げる
- ゆっくりと元の位置まで下ろす
背もたれに背中を付けた状態でやるのがポイントです。
バーの握る位置によって、肩の前側を鍛えることもできます。
ショルダープレスについては「ショルダープレスのやり方や効果を最大化させる方法を解説」も参考にしてください。
アームカール
アームカールは前腕を鍛えるトレーニングです。前腕を鍛えることで、力こぶを作れます。
アームカールのウエイトマシーンがおいてあるジムは少ないので、ダンベルで代用するのがおすすめです。
アームカールは、下記のようにやります。
- 手のひらを上にしてダンベルを握る
- 肘をわき腹に固定する
- ダンベルを持ち上げる
- ダンベルを下す
ダンベルを持ち上げたり、下ろしたりするときは、肘の位置を動かさないようにしましょう。疲れてくると下ろす距離が短くなってしまうので、肘が伸びきるところまで下ろすのを意識してください。
アームカールについては「アームカールのやり方と効果を最大化させる方法を解説」も参考にしてください。
フレンチプレス
フレンチプレスは二の腕(上腕三頭筋)を鍛えるトレーニングです。二の腕の引き締めや、たるみの解消に効果があります。
フレンチプレスのやり方は、下記のとおりです。
- ダンベルを両手で持ち、頭の上に持ち上げる
- 背中側に肘を曲げる
- 肘を曲げたら、頭の上に持ち上げる
肘が90度になる位置まで曲げましょう。トレーニングは可動域が大きくなるほど、効果が高くなります。ダンベルを持ち上げるときは、天井に向かって押すように持ち上げるのがポイントです。
フレンチプレスする時はダンベルだけでなく、プレートなども利用して鍛えられます。
フレンチプレスについては「フレンチプレスのやり方と効果を最大化させる方法を解説」も参考にしてください。
クランチ
クランチは腹筋を鍛えるトレーニングです。シックスパックに割れた腹筋や、くびれのあるお腹を作るのにおすすめ。
クランチのやり方は、下記のとおりです。
- 床に軽く膝を曲げて、仰向けで寝る
- 手を太ももの上におき、擦りながら上がる
- 元の位置にゆっくりと戻る
上体は最後まで起き上がらせる必要はありません。40度ほど起き上がっていれば、腹筋に効果があります。
腹筋するときに、手を頭の後ろで組むのをやめましょう。疲れてきたときに手で上げてしまい、いきおいで首をケガしてしまうこともあります。手の位置は太ももの上に置くのがおすすめです。
クランチについては「【お腹痩せ筋トレ】クランチの正しいやり方と効果を高める方法」も参考にしてください。
レッグレイズ
レッグレイズは腹筋の下部を鍛えるトレーニングです。ポッコリお腹の改善や、下腹が出てくるのを防ぐ効果があります。
レッグレイズのやり方は、下記のとおりです。
- 脚を天井に上げて、仰向けで寝る
- 脚を床に向かって下ろす
- 脚を床ギリギリまで下げたら、ゆっくりと持ち上げる
脚を下した時に腰が痛い人は、手をお尻の下に入れることで軽減できます。
足を伸ばした状態でやるのがきつい人は、膝を90度に曲げた状態から、曲げ伸ばしをするのもおすすめです。
レッグレイズについては「【下腹部の筋トレ】レッグレイズの正しいやり方と効果的な方法」も参考にしてください。
増量期と減量期を使い分けてボディメイクしよう!

ボディメイクするには増量期と減量期を分けることが重要です。
増量期に身体を大きくして、減量期に余計な脂肪を削ることで、たくましい体を手に入れられます。
特に今よりも筋肉をつけたい人は、増量期と減量期を意識してきて取り入れましょう。
増量期と減量期をマスターして、理想の身体を手に入れてください。
トレーニングにおすすめの関連記事
トレーニングのレベルを向上させたい人や、トレーニングの効率を高めたい人はギアや、グッズ、プロテイン、宅食サービスを利用してみましょう。
トレーニングアイテムを揃えることでトレーニングパフォーマンスの向上や、ケガの予防に効果があります。また、プロテインや宅食サービスを利用することで、トレーニングの効果を高めることも。
下記の記事でおすすめのアイテムや、宅食サービスを紹介しています。

パーソナルトレーニングジムポータルサイト「Choice GYM’s」
全国各地でおすすめのパーソナルトレーニングジムを紹介しています。
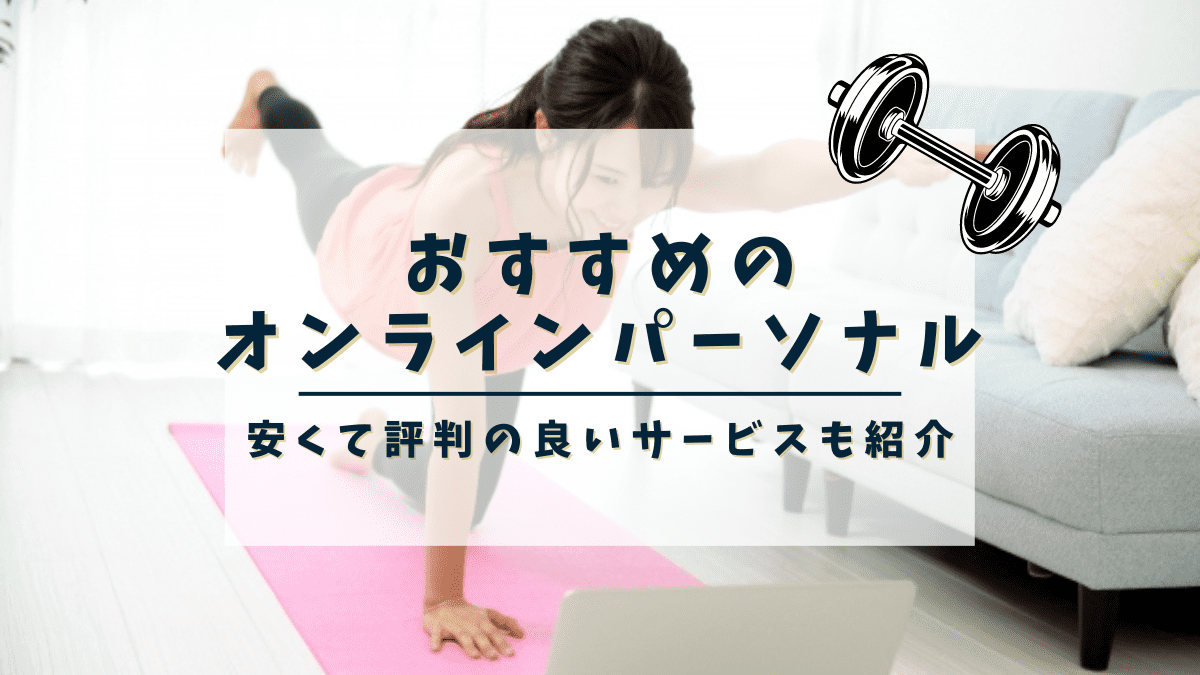
オンラインパーソナルトレーニングおすすめ9選!
自宅でも専門知識豊富なトレーナーから、トレーニング指導が受けられると人気のおすすめのオンラインパーソナルトレーニングサービスを紹介しています。

筋トレ・ダイエットにおすすめの宅配弁当4選
筋トレやダイエットしている人におすすめの宅食サービスを紹介しています。食事管理が苦手な人や、自炊する時間がない人におすすめです。

筋トレにおすすめのトレーニングギア8種
自宅で筋トレを頑張りたい人や、自重トレーニングの効率を高めたい人におすすめのトレーニンググッズを紹介しています。

目的別おすすめの人気プロテインを紹介
筋トレ後におすすめのプロテインや、ダイエットに効果的なプロテインを目的別で紹介しています。

筋トレ器具おすすめ14選!自宅で使いやすい商品を紹介
自宅で筋トレを頑張りたい人や、自重トレーニングの効率を高めたい人におすすめのトレーニンググッズを紹介しています。
参照文献


